第61回 Hip Joint コラム

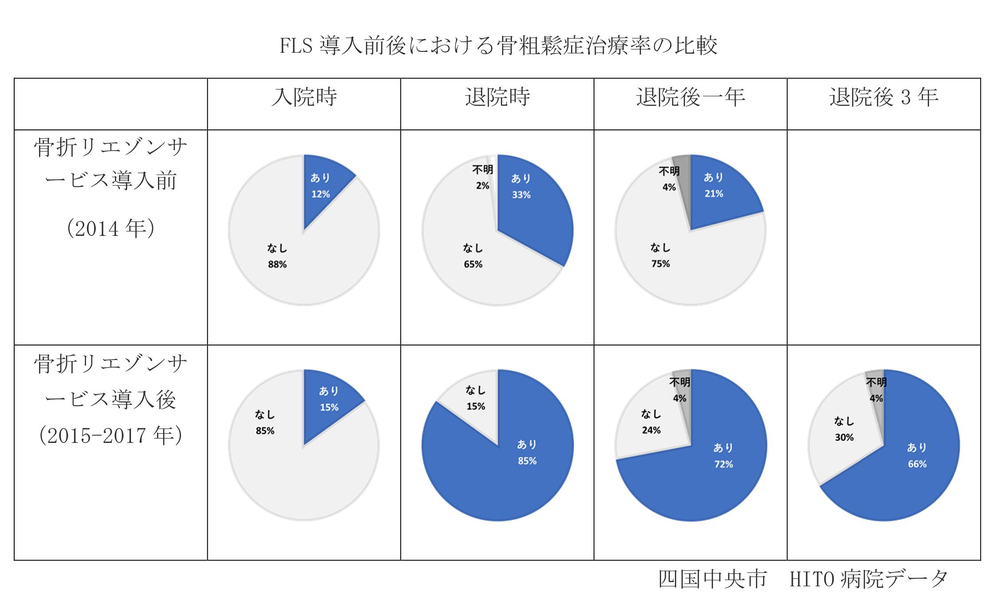
第123回 「一般の方々に向けた股関節の予防と治療のガイドブックについて」
第119回 「人工股関節置換術の進化 〜より安全・正確な手術を目指して〜」
第114回 「関節手術の患者になって実感したリハビリの重要性」
第113回 「股関節周囲筋の術前筋組成は人工股関節置換術後の歩行機能回復と関連している」
第111回 人工股関節置換術、前・後の生活の質(QOL: Quality of Life) について
第108回 「人生100年時代を生きる! 運動器とロコモ予防の大切さ」
第103回 健康日本21(第3次)における運動器対策:
「ロコモテイブシンドロームの減少」と「骨粗鬆症検診率の向上」
第102回 「股関節周囲筋の加齢変化と、根拠に基づいた運動療法」
第101回 「原因の分からない股関節痛、急速破壊型股関節症の始まりかもしれません」
第95回 「大腿骨近位部骨折のリスクを下げるために出来ること」
第94回 「手外科医として,整形外科研究者として股関節外科から学ぶ」
第93回 「人工股関節置換術の進歩と課題:第96回日本整形外科学会学術総会から」
第85回 「ロボットリハビリテーション 股関節疾患への応用」
第80回 「骨粗鬆症治療中に注意が必要な骨折−大腿骨非定型骨折−」
第69回 子どもや孫が「家族歴」が理由で
股関節健診にひっかかった!!時に読む記事
第66回 人工股関節全置換術術後でも足の爪が
自分で切られない患者様に対する自助具を開発しました!
第57回 赤ちゃんの股関節を守るため、生まれてすぐからの予防を!
第52回 2020年(令和2年)新春明けましておめでとうございます。
第36回 ステロイド治療に伴う大腿骨頭壊死の発生予防を目指して
第33回 大腿骨近位部骨折(足の付け根の骨折)は早く治療を!
第29回 大腿骨近位部骨折が増加しています-50歳を超えたら骨折予防-
第24回 新しい高齢者像を求めて、メディカルフィットネス 医学体操の活動
第15回 「骨粗鬆症の激増と過激な減量、ビタミン・ミネラル不足」